【アクセシビリティマップ制作プロジェクト】車いすに乗って、拠点のバリアを見つけ出せ!~目黒ビル編~(2024年9月)

くらしアプライアンス社(LAS社)DEI・組織開発室は、"心のバリアフリー"をテーマに、継続して誰もが働きやすい環境づくりを推進しています。有志メンバー10名と人事・総務メンバーが集まり、計18名で草津および目黒拠点のアクセシビリティマップを制作するプロジェクトが24年9月に本格的スタート。拠点の環境マップ化に向けて、実際に車いすに乗りながらバリアを調査中です。今回は目黒ビルでの様子をお届けします。
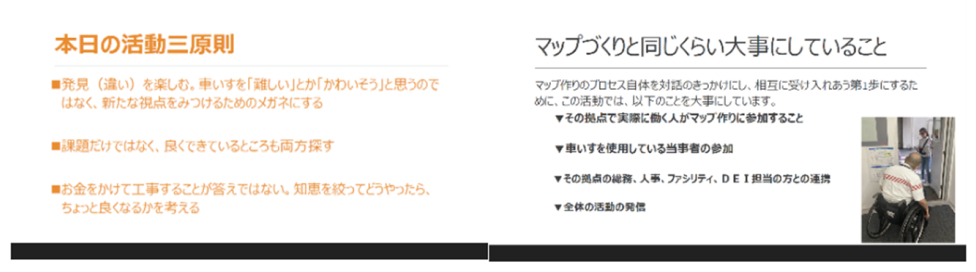
9月上旬には、パラスポーツ・パワーリフティング選手でパナソニックのDEIアドバイザーでもある山本恵理氏をパナソニック目黒ビルにスペシャルゲストとして迎え、日常にすっかりなじんでいる景色の中にもバリアはたくさん潜んでおり、活動三原則の下(上記スライド参照) 、"まずは見つける"大切さをお話しいただきました。


活動では、部屋から車いすに乗って出発しましたが、いきなりドアをうまく開けられないという事態に。
この部屋のドアが手前に引く開き戸だったからです。開き戸を開くコツは、手前に引いてできた少し隙間に車いすをねじ込ませて、車いす本体で押しながら開けること。腹筋が発達していない方が多いため、車いすユーザーにとって押したり引いたりしないといけない開き扉は開けることが非常に難しいそうです。
このとき、「○○棟のドアは開けにくい」とマップ上に記すことは正解ではなく、「誰かのサポートがあったらうれしいエリア」と記載するなど、できないことばかりに注目するのではなく、前向きな内容で記すことが大切というアドバイスをいただきました。
なお、扉が引き戸になると、開けやすさが格段に上がります。
その後、目黒ビル1階に移動しました。1階は家電製品を展示しているスペースですが、肝心な製品説明の札が車いすの視点からは見えないことに気が付きました。一方、昔の製品を紹介しているコーナーでは説明が見やすく、札の設置方法を変えるという小さな工夫だけでも、情報を受け取れる人は大きく増えることを学びました。


このような工夫は、車いすユーザーに限らず、例えば背が低い子どもにも効果的です。車いすユーザーのための取り組みは、より多くの人にとって心地の良い目黒ビルづくりにつながることを改めて実感しました。
車いすを乗っている状態では、人によっては自動販売機の一番上のボタンに届かず、上に設置されている商品は購入できない可能性があることに気付きましたが、飲み物の配置の仕方で乗り越えられるかもしれないといったアイデアがメンバーからあがりました。通常、自動販売機では同じ商品を数個横並びで販売していますが、縦並びでそれぞれの段で販売すれば、ボタンの位置の選択肢を増やすことができます。ボタンの位置が低い自動販売機を新たに導入すると費用がかかってしまいますが、ちょっとした工夫次第で、既にあるリソースでバリアを乗り越えることができます。メンバーの知恵を生かしてバリアの乗り越え方を模索することも、アクセシビリティマップを制作するうえで重要な要素です。
今回のバリア探しに関して、プロジェクトリーダーの大美さんは次のように振り返っています。
バリアに出会う度、初めは難しそうな表情をしていたメンバーですが、調査を通じて、バリアをポジティブに変換できるようになり、表情もどんどん明るくなっていると感じます。「設備投資のお金がない」「インフラが整っていない」など、"ない発想"から「バリアは工夫次第で乗り越えられるもの」と代替案を考えていくマインドに変化しました。まさに心のバリアフリーです。
私たちは、バリアを見つけて指摘するネガティブな活動を目指しているわけではなく、より多くの人が目黒ビルで快適に過ごせるよう現状を理解し、障壁を打破していくというポジティブな目的意識を持って取り組んでいます。
調査中、優しく声をかけてくれたり、サポートしてくれたりする社員も多々おり、優しさの重要さを実感したことも大きな収穫です。
周りの協力があってこそ、一人では乗り越えることが難しいバリアを乗り越えられると思うからです。今後も本活動を推進していきます。

