DEIの取り組み
パナソニック株式会社のDEIの取り組みをご紹介します。
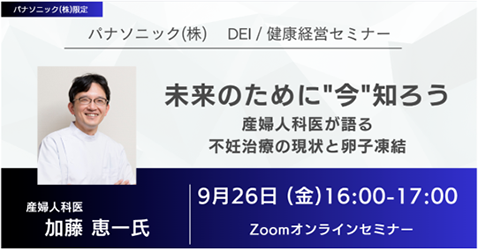
プレコンセプションケアセミナー「未来のために“今”知ろう」を実施(2025年9月)
不妊治療や卵子凍結に関するプレコンセプションケアセミナーを開催しました。外部講師に加藤レディスクリニックの産婦人科医 加藤恵一氏を招き、不妊治療の現状や職場でのサポート方法をお話いただきました。
参加者の約8割が内容に満足と回答、「職場や上司に知ってもらう場としては有意義だった」「自分のキャリアも含めた人生設計について考えるきっかけになった」という声もありました。
不妊治療や妊活は、実際に経験した人でなければわからないことがたくさんあります。また、その実態や悩みは当事者以外の方にとって、あまり知られていない状況です。当社は、今後とも正しい知識を普及し、職場理解と信頼関係を促進し、組織の持続性向上を目指してまいります。
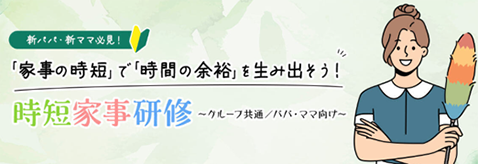
セミナー「時短家事研修」を実施(2025年9月)
家事の時短で、時間の余裕を生み出すことを目的に「時短家事研修」を開催しました。
時短家事コーディネーター®Basic認定講師の井上ひろみさんをお招きして実施。時間の使い方を可視化することや、自身の悩みをグループワークで共有しました。今回は、新米パパママの家事と育児の両立だけでなく、介護と家事の両立に悩む社員も参加できるよう対象範囲を拡大、すぐに実践できる内容を学びました。参加者からは「学んだ考え方は家事だけではなく、業務でも活かせそう」という前向きの声もありました。

体調ナビゲーションサービス「RizMo」活用による 女性の健康行動支援と組織パフォーマンスへの効果を検証(2025年8月)
くらしアプライアンス社は、経済産業省が推進する令和7年度「フェムテック等サポートサービス実証事業費補助金」事業者に採択され、女性の健康課題解決と企業の多様性推進を目的とした実証事業を実施することとなりました。体調ナビゲーションサービス「RizMo(リズモ)」を活用し、女性社員や他企業の協力のもと、ヘルスリテラシー向上や組織パフォーマンスへの効果を検証。これにより、フェムテックの効果や多様性推進の社会的意義を広く検証し、ウェルビーイング向上を目指します。
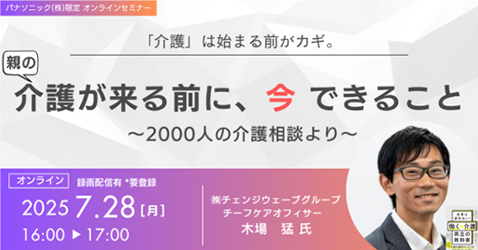
セミナー「介護が来る前に、今 できること」を実施(2025年7月)
介護前に何ができるのかを知る機会提供として、セミナー「介護が来る前に、今 できること」を開催しました。
外部講師に㈱チェンジウェーブグループCCO木場猛さんをお招きして実施。事後アンケートでは約8割の参加者が親の介護に対する不安が「軽減された」と回答、「非常にわかりやすく、漠然と不安を抱いていたものが、かなり解消されました」という感想もありました。
講演の中で、パナソニックホールディングス㈱が内閣府SIP(戦略的イノベーション創造プログラム)において開発中の”フレイル予防サービス”の紹介もあり、親の介護を先送りするという手段に気づく機会となりました。

「イクボス研修」「プレパパママ研修」を実施(2025年6ー7月)
当社は、パナソニック コネクト株式会社、パナソニック インダストリー株式会社と合同で、育児休業取得推進・理解を目的に、上司向け「イクボス※研修」と「プレパパママ研修」をオンラインで開催しました。
外部講師にNPO法人 ファザーリング・ジャパンの塚越学さんをお招きして、上司にはチーム作りという視点で、当事者にはキャリアを考えるきっかけになるような内容で実施。いずれの研修も満足度4.7(5点満点中)と高く、参加者からは「育児休暇は組織としても個人としても仕事の見直しや成長のチャンスである」といった声もありました。男性育休取得率の向上と意識醸成を目指し引き続き活動を推進してまいります。
※イクボスとは「部下の育休取得や短時間勤務などがあっても、業務を滞りなく進めるために業務効率を上げ、仕事と私生活を両立できるように配慮し、自らも仕事とプライベートを充実させている管理職のこと。

女性の健康課題を考える「みんなのウェルビーイングデー」を開催(2025年6月)
くらしアプライアンス社は、2025年6月25日、男女共同参画週間に合わせ「みんなのウェルビーイングデー」を開催しました。ポットキャスト配信ユニット「ハダカベヤ」のIMALU氏、メグ氏、なつこ氏と、慶應義塾大学SFC研究所 上席所員で女性健康科学者の本田 由佳氏などをお迎えしトークセッションなどを実施。社員約300名が参加し、女性の健康課題やフェムテックについて考えました。また当社フェムテック初の体調ナビ「RizMo」や他社の製品展示も行い、多様性と健康意識向上を推進しました。当社は、性別や背景に関わらず、誰もがより良い暮らしを享受できる社会の実現を目指してまいります。

東京で実施されたTokyo Pride 2025のパレードに参加(2025年6月)
アジア最大級のLGBTQ+の祭典「Tokyo Pride 2025」が6月7日と8日に開催されました。6月8日に渋谷・原宿周辺で開催されたPride Parade(プライドパレード)では約1万5000人が行進し、パナソニックグループから総勢250名(パナソニック㈱からは25名)が参加しました。
Tokyo Pride 2025のテーマ「Same Life, Same Rights(=同じ命、同じ権利)」は、LGBTQ+コミュニティをはじめ、すべての人々が平等・公平に生きる権利を持つというメッセージを訴えています。当社は本活動を通して社内外にLGBTQ+支援の姿勢を表明し、DEI推進をより加速してまいります。

子育てサポート企業として「くるみん認定」を取得しました(2025年3月)
パナソニック株式会社は、2025年3月17日に厚生労働大臣の認定制度である「くるみん認定」を取得しました。

グループ2社と合同で「育休復帰前セミナー」を実施(2025年3月)
当社はパナソニック コネクト株式会社、パナソニック インダストリー株式会社と合同で、育児休業取得中の従業員とそのパートナーを対象に「育休復帰前セミナー」を、2月22日にPCO 京橋拠点、3月1日にPCO 浜離宮拠点で実施しました。
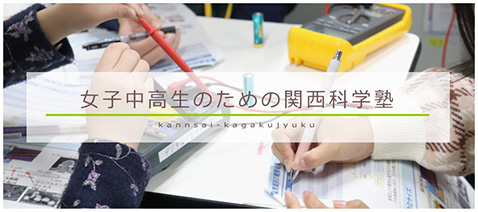
「女子中高生のための関西科学塾」に協賛(2025年1月)
くらしアプライアンス社(以下、LAS社)は、一般社団法人関西科学塾コンソーシアムが運営する「女子中高生のための関西科学塾」に協賛しました。LAS社は全社員の約30%が技術系の社員であり「理工系の学術分野のおもしろさやさまざまな理工系の仕事があることを伝えたい」という同塾の目的に共感したことに加え、女性活躍推進に力を入れていることから、女子中高生の理工系分野の進学を後押ししたいという想いで協賛を決めました。

メディア発信~管理職は強くなくていい。「私らしい」ワークとライフの見つけ方~(2025年1月)
リーダーのあり方、仕事と家庭の両立、今後のキャリア形成などをテーマに、パナソニックの課長として活躍する社員とSHE株式会社代表取締役 / CEO・CCOの福田恵里さんのインタビュー。

CHRO対談 仕事と介護の両立、ビジネスケアラーの課題(2024年12月)
当社はExcellent Care Company Club(エクセレント・ケア・カンパニー・クラブ)という、企業横断でビジネスケアラー課題に取り組むコンソーシアムに参画しています。同コンソーシアム企画運営を担う、株式会社チェンジウェーブグループ代表取締役社長CEOの佐々木裕子さんと当社CHROの加藤の対談です。

女性活躍推進法に基づく優良企業として、「えるぼし認定」3つ星を取得(2024年12月)
パナソニック株式会社は女性活躍推進法に基づき、女性の活躍に関する取組の実施状況が優良な企業として厚生労働省が認定する「えるぼし認定」において、最高位である3つ星を取得しました。 当社は、厚生労働省が定める5つの項目 (1)採用、(2)継続就業、(3)労働時間等の働き方、(4)管理職比率、(5)多様なキャリアコース の基準に応じて3段階で評価されました。引き続き一人ひとりがその能力を発揮できるような雇用環境の整備を目指してまいります。

PRIDE指標2024ゴールドを獲得(2024年11月)
パナソニック株式会社は一般社団法人work with Prideが、職場におけるLGBTQ+などのセクシャルマイノリティに取組む企業・団体を評価する「PRIDE指標2024」において、「ゴールド認定」を獲得しました。

経営責任者セミナー「経営におけるDEI ~個の違いこそが経営を強くする~」を開催(2024年11月)
DEIをテーマにした経営責任者セミナー「経営におけるDEI ~個の違いこそが経営を強くする~」を開催しました。DEI推進担当の、当社CEO品田と分社長をはじめ、各組織の経営層がオンラインで参加しました。セミナーの第一部では、外部講師として西村優子氏(株式会社リクルートホールディングス 人事統括部 部長 兼サステナビリティトランスフォーメーション部 部長 兼 IR, ESGコミュニケーション Lead)による同社での取組みを、また当社代表事例としてエレクトリックワークス社社長の大瀧から同社での取り組みを紹介しました。第二部では、DEI推進担当と西村さんによるトークセッションを実施し、経営におけるDEIの重要性を発信しました。

大阪で実施されたレインボーフェスタ!2024のパレードに参加(2024年10月)
10月27日に開催されたレインボーフェスタ!2024のパレードにパナソニックグループから総勢190名(パナソニック㈱からは46名)が参加しました。レインボーフェスタとは国内外に暮らすあらゆるセクシュアリティとALLYの人々が多様性を祝う関西最大級のイベントです。参加した社員はLGBTQ+への理解を深めるとともに、実際に当事者と触れ合うことで支援の重要性を実感しました。この活動を通して社内外にLGBTQ+支援の姿勢を表明し、DEI推進をより進めてまいります。

【アクセシビリティマップ制作プロジェクト】車いすに乗って、拠点のバリアを見つけ出せ!~目黒ビル編~(2024年9月)
当社拠点の一つ、目黒ビルでアクセシビリティマップの制作に向け調査を実施。車いすでいつも何気なく使っているオフィスや通勤経路を違った視点で回ることで、これまで想定できていなかった過ごしづらさを感じました。見つけたバリアを乗り越えるためには、必ずしも金銭の投資だけで解決しようとするのではなく、知恵を絞って今ある設備を工夫する解決法があることに気づき、心のバリアフリーを体現する機会となりました。

女性管理職ネットワークを立ち上げ、キックオフミーティングを開催(2024年8月)
エレクトリックワークス社(以下、EW社)では、2024年度に初めて管理職の女性が100名を超えたことを受け、女性管理職のネットワーク形成のため8月22日にキックオフミーティングを開催しました。このミーティングではEW社の経営幹部も参加し、ジェンダーギャップ解消に向けたディスカッションを実施、DEI推進について深く考える貴重な機会となりました。

ゴールドパートナーとして国際女性ビジネス会議に出席(2024年8月)
「ダイバーシティ視点がイノベーションを生み出す」という国際女性ビジネス会議(主催:株式会社イー・ウーマン)の趣旨に賛同し、2年連続でゴールドパートナーとして参画しました。くらしアプライアンス社社長の堂埜が「新しい事業を切り開く」をテーマに掲げたトークショーに登壇したほか、テーマ別ディスカッションを行う円卓会議には女性幹部社員が参加しました。また、会場に設けられた企業ブースでは、総勢約40名からなる調理ソフト開発者の専門メンバーで構成されたPanasonic Cooking@Labが出展し、モノづくりへの想いを伝えました。

製造現場で働く「女性リーダーTalk2024」を開催(2024年6月)
パナソニックFT職能開発研究会(FT研)は6月20日と21日の2日間、製造現場の女性リーダーを対象に、 DEIの観点を取り入れながら現場での困りごとや新しい現場の形について考える「女性リーダーTalk」をパナソニックセンター東京で実施しました。全国の製造拠点で活躍する32名が参加、女性リーダーたちが日頃はなかなか話しにくい悩みや課題を共有し、組織のジェンダーギャップの解消と自身のキャリアについて考える機会となりました。

多様な働き方を体現する「トモダテ」研修(2024年6月)
くらしアプライアンス社の社内アンケート調査から、社員が「男性育休」を取得しない理由として、「休みにくい」「職場で制度を利用しづらい雰囲気」といった職場に向けての気遣いが多く、自身の子育て参加への優先度が下がっているという課題が浮かび上がりました。そこで、これから男性育休を取得する社員向けに「共に子育てをする“トモダテ”」の意識を育む独自内容で、ワークショップ形式の研修を実施。参加者からは、「家事・育児について、妻と話すきっかけになった」などの声が寄せられました。

部門横断型アクセシビリティマップ制作プロジェクト(2024年6月)
障がいの有無に関わらず、誰もが各拠点へ安心・安全にたどり着けるよう、拠点の環境を可視化するアクセシビリティマップの制作が目黒拠点と草津拠点でスタート。メンバーは、先行してこの取り組みを行った彦根拠点の従業員と意見交換をしました。また、特例子会社のパナソニックアソシエイツ滋賀を訪問し、障がい者が過ごしやすい環境について学びました。

女性役員と女性のライフ・キャリアを考えるラウンドテーブルを実施(2024年5月)
ワークライフバランスなど女性が感じる課題や想いを、女性幹部のキャリアの振り返りや質疑を通じてキャリア形成を後押しする目的でパナソニック ホールディングス参与の小川理子による「女性のライフ・キャリアを考えるラウンドテーブル」を実施しました。参加メンバーからは、「経歴や、その時々に感じて実行してきたことを直に聴けたことで、今の自分の立場に置き換えた時、勇気を貰えた」などの前向きな声が集まりました。

パナソニック アソシエイツ滋賀が取り組む従業員一丸で対話し続ける環境づくり(2024年4月)
くらしアプライアンス社傘下の特例子会社、パナソニックアソシエイツ滋賀では、障がいのある社員が多く働いています。障がいの程度は様々で、必要な配慮や得意・不得意とすることも十人十色です。多様な社員が働いているアソシエイツ滋賀では、一人ひとりが力を発揮して働ける環境づくりのために、一人ひとりに合わせたハード面の配慮とコミュニケーションから生まれる関係性の両方を大切にしており、当事者だからこその気付きを元にした工夫が随所に施されています。

新入社員研修の一環として182名がパラスポーツに挑戦(2024年4月)
24年度のくらしアプライアンス社新入社員研修の一環として、パラスポーツ運動会を実施しました。新入社員182名が一丸となり、車いすリレーなど全3種目に挑戦。普段とは違う視点での体験を通じて仲間と協力することの大切さに気付き、同期間での交流が深まりました。また、障がいの有無に関わらず全ての人が楽しめる工夫が施されたパラスポーツを体験することで、互いの違いを尊重するとともに、誰もが輝ける仕組みづくりの重要性やそのヒントを学びました。
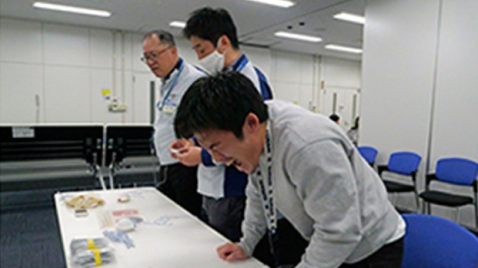
生理痛体験などフェムテックに関する独自プログラムを実施(2024年4月)
「フェムテック活用が人的資本経営に及ぼす影響に関する実証実験」において、性別による違いを理解し合える風土醸成を目指し、当社が抱える具体的な課題にフォーカスしつつも、性別や年代を超えて多くの社員が関心を持ちやすい独自プログラムを提供。フェムテックを中心とした福利厚生プログラムに加えて、生理痛体験プログラムやDEI対談イベントを実施しました。その結果、性差に関わらずコミュニケーションの活性化や社員の意識変革につながるという、フェムテックの活用効果が得られました。

