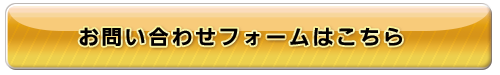第36回:シリーズ『スマートな工場管理へのステップ』(1/2)

本シリーズでは、『スマートに管理された工場』を一つのゴールとして、その実現に向けた現実的なステップについて考察しています。最終回となる今回は、シリーズのゴールである「スマートに管理された工場」をどう実現するかについてお話しします。
ゴールに向けた最終ステップ
前回、本稿で目指す「スマートに管理された工場」の前段のステップとして、以下の方法についてお話ししました。
異なる工程の連携によって『原料-中間材-製品』という一連のデータを管理し、在庫・品質の安定管理を実現する。
これは、工場内の全工程を俯瞰的にとらえ、「製品」から「原料」へと遡(さかのぼ)るためのトレーサビリティを確保する取り組みです。原料と中間材、製品の品質データを紐づけて管理することで、トレーサビリティを確保し、不良品発生時に、製品を構成する原料にまで遡り、原因を解明することを可能にします。また、こうした品質データとIoTを通じて収集した設備データを併せて管理することで、設備の状態と品質との因果関係についても解明できるようになります。
さらに、品質データの管理によって、製品ロットごとの品質データの「回帰(傾向)分析」を行うことも可能になります。つまり、製品ロットごとの品質データの傾向を分析・比較して、他のロットとの大きな傾向差異が認められるロットを見つけ出し、品質異常を検知するというわけです(図1)。

このように、工場の各工程のデータを連携させながら管理することで、製品品質の安定化と、製品不良発生時の原因究明が効率化されます。今回は、この次のステップとして、いよいよ「スマートに管理された工場」の実現を目指します。
スマート工場の実現方法
本稿で言う「スマートに管理された工場」とは、「Industry 4.0」などでも提唱されているスマート工場を指しています。
そのスマート工場を実現する方法の一つは、工場のMES(製造実行システム)のデータと、全社の基幹業務を支えるERP(基幹系情報システム)のデータ(外注管理・在庫管理・調達管理のデータ)をリアルタイムに連携させることです(図2)。

このようにERPとMESのデータをリアルタイムに連携させる大きな目的の一つは、経営視点で各工場の稼働や在庫を適正化し、コストの最適化につなげることです。また、ERPとMESのリアルタイムなデータ連携は、販売部門での販売可能在庫の正確な把握や納期回答の迅速化にもつながっていきます。
一般的に、MESは工場内に閉じたシステムとして構築・運用される傾向にあり、多くの製造企業でERPとMESとの連携が課題とされています。
同様に、MESの在庫情報とERPのリアルタイム連携も実現されていないことがあり、その場合、MESとERPの在庫情報の整合性はバッチ処理によって確保されています。そのため、本社側、あるいは本社の販売部門は、前日までの在庫情報しか正確に把握できていないケースが多く見られます。
さらに、工場の生産管理/計画のシステムも、ERPと連携していないことが多く、結果として、急な大量発注が発生した際に、販売部門は正確な納期を顧客に即答できず、販売機会を逸するリスクを背負ってきました。また、工場内に閉じた生産管理/計画のシステムは、想定外の発注に応じて、自動的に最適な生産計画を組み直す機能が実装されていない場合も珍しくなく、想定外の大量発注への対応を生産側が求められた際には、生産管理の担当者が手作業で計画を練り直し、事態の収拾に当たることが多かったと言えます。
市場ニーズの変化が少なく、生産した製品が、ほぼ計画どおりに売れていた時代では、工場は当初(期初など)に立てた稼働率目標に沿って生産を回していればよく、MESとERPとのリアルタイムなデータ連携もそれほど必要ではありませんでした。
ところが、今日のような変化の時代では、予想を超える大きな変動がいつ発生しても不思議ではなく、稼働率目標に沿って生産の効率化を推し進めても、生産している特定製品の需要が突然落ち込み、在庫が想定外に増えてしまうリスクも膨らんでいます。
工場がそのような市場の変化にスピーディーに対応するためにも、また、経営層が変化に対するタイムリーで的確な意思決定を下すためにも、MESとERPとのリアルタイムなデータ連携は不可避となりつつあるのです。
バックナンバー
商品に関するお問い合わせ
パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社 お問い合わせ受付窓口
電話番号: 0570-087870 受付時間: 9時~12時、13時~17時30分(土・日・祝・当社指定休業日を除く)